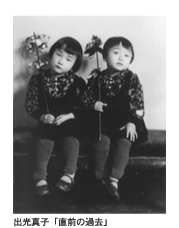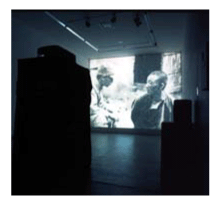「Borderline Cases 境界線上の女たちへ」展の内容とシンポジウム
それでは,Borderline展には実際にどのような作品が出品され,結果としてどんな人々の間でどのような「応答」がなされたのだろうか。
参加アーティストと出品作品のリストは,本文の末尾に掲げたので参照していただきたい。1階と地下からなるA.R.T.のスペースはさほど広くはなく,ここに5人のアーティストの作品が展示され,2人のパフォーマンス公演が行われることは,正直,2月のプレ・イヴェントの時には予測もつかなかった。しかし地下のスペースで,初日の5時にイトー・ターリ,高橋芙美子のパフォーマンスが上演され,2時間のインターヴァルの間に,同じ地下スペースにハッキョン・チャと出光真子のヴィデオ・インスタレーションが設置されるという早業を駆使して,見事に展示が完成した。会場構成や出品作家の決定は,最終的にゲスト・キュレーター,キム・ソンヒ(光州市立美術館→森美術館キュレーター)の責任においてなされたという。
パク・ヨンスクの《マッドウイメン》シリーズは,2002年の光州ビエンナーレに出品して注目を集めたもので,韓国の男性中心の社会制度(家父長制)のなかで貧困と抑圧に追い込まれて来た女性たちの声を代弁する意図をこめた作品である。2002年のシリーズでは,パク・ヨンスク本人や尹錫男(ユン・ソクナム)をはじめ,友人の女性たちがモデルを務めたが,彼女たちは男性の作った社会通念や固定概念に反抗したために,「気が触れた女」「魔女」と言われて精神を病んだものとされて来た,祖母や母,妻,姉,娘たちなどを演じることで,すべての女性の気持ちを代理経験し,分かち合うのだという。抑圧されて狂気に追いやられる女というと暗く重苦しく聞こえるが,パクの作品は作者とモデルのたくましい個性を反映して、イデオロギーを逆転する明るいユーモアと、破壊の力が篭められている。今展では,先の大阪での滞在期間に,日本のフェミニストたちをモデルに制作された新作が展示された。男性中心の社会制度は日本でも韓国と同様だが,日本の女性たちの「狂気」は,韓国の女性よりもドラマ性が少なく、日常的で内面に沈潜して見え、その奇妙な静けさによってかえって抑圧の根が深く見えた 。さらにこの会期中に,東京のフェミニスト女性をモデルにして新作が撮影されたというので,それも併せて見る機会を待ちたい。
尹錫男(ユン・ソクナム)の《お母さんの19歳》は,1993年に制作された母の彫像に,娘時代の母と友人の写真を大きく引き伸ばしたものと,母を中心としたユンの家族の物語をたどる5点の素描を組み合わせたインスタレーションである *13 。ユン・ソクナムもまた,韓国の家父長制社会のなかで生きてきた女性の苦難を,「母の眼」を通して語ってきた作家であり,ユン自身が40歳を越えてから制作をはじめ,私は誰か,何のために生きているのか,私がここに存在していないという女性たちの気持ちを,作品に表わしてきた。捨てられた木片を組み合わせて作られる女性の身体は,男性が理想とした完璧な美しさや性的魅力からは遠く離れて,不完全でいびつに曲がっている。しかしそこには,女性として同じ思いを抱いたことのある者の心を捕らえて離さない,哀しみと温かさと強さがこめられている。「フェミニストのアーティスト」に向けた,男性批評家の紋切り型の解説では,ユン・ソクナムの芸術の豊かさが零れ落ちてしまう*14 。

こうした韓国のアーティストの「家父長制」下の「歴史」や「社会」が規定した「女性」の境界を越える表現に対して,日本のアーティストはどのように応答しただろうか。嶋田美子の《箪笥の中の骨》Family Secretsは,小引き出しのついた箪笥と版画,カーテンで囲まれた机と椅子からなるインスタレーションである。引出しを引くと,中には在日の家族の秘密が写真と文字で書かれている。しかし観客は他人の秘密を覗き見る後ろめたい体験に終わるのではなく,自分自身の家族の秘密をカーテンで隠された机に向かって紙に書き,設置された箱に入れるように指示される。秘密を抱えているのは,日本社会の中のマイノリティである在日韓国・朝鮮人の家族ばかりではなく,マジョリティである日本人の家族も同様ではないか。嶋田美子はこう問いかけ,「家族」という装置が社会から隠蔽し,「闇」に葬ってきた物語を,匿名のまま,社会に公表することを誘う。嶋田の誘いに答えて秘密の紙片を箱に入れた観客はどのくらいいただろうか*15 。観客の秘密は今後嶋田によって作品にされ,引き出しの中の作品と入れ替えられるという。
出光真子の《直前の過去》も,1940年生まれの出光と姉の幼年時代の家族写真から始まる。彼女の幼年期は,ちょうどそのまま日本のアジア侵略と太平洋戦争に重なっていた。姉とおそろいのドレス姿の幼女,美しい母のいる家族写真、彼女の回想する「穏やかでのどかな日常生活」の映像がリピートしているが、観客が入り口(ボーダー)を越えるとセンサーが作動して、まさに同時代の日本軍の戦争映像に一変する。巨大な軍艦,戦車,占領地での日本語教育,従軍「慰安婦」にされた過去を語る老女,慰安所規定,逃げまどう中国の難民たち,日本軍による中国人の処刑,特攻隊の出撃,撃墜される特攻機,二重橋に立つ白馬の天皇,そして召集された兵隊の行進は,靖国神社の大鳥居にオーヴァーラップされる。戦時の記録映像を継ぎ合わせて,出光真子が作り出したのは,平和な日常に安閑とする市民生活と軍の動きの激しい乖離であり,それは1940年代に限らないこと,否応なく現在の状況に重ねられることを,強烈なイメージで訴えてくる。そして日常から戦争への「境界」を踏み越えるのは、何と容易なことかを体感させてくれる。戦争は遠い昔ではなく,直前の過去であり,また現に目前に迫っているのかも知れないと。
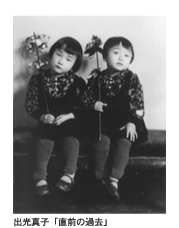 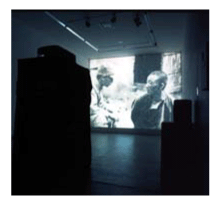
イトー・ターリのパフォーマンス《虹色の人々》も,セクシュアル・アイデンティティ,在日,家族,社会という個人的な問題から,イラク戦争に加担する現在の日本の状況という政治的問題に開いていく。それは二人の友人との対話の音声で始まった。一人は,宮本百合子との同性愛関係に踏み込んだ湯浅芳子の評伝を出版するにあたって,それまでのペンネームではなく実名を使うことにしたレズビアンの女性ジャーナリストであり,もう一人は大学に入って初めて朝鮮語を学び,朝鮮名を名乗ることにした在日朝鮮人の女性である。彼女たちは,マイノリティであることを実名によってカムアウトしたことにより受ける社会からの拒絶や疎外と,それにもかかわらず実名を名乗らずにいられない,自己の内的な必然性について語る。誰もいない船の甲板で踊る自身の映像を背景に、白いウィッグをかぶったターリは踊りながら鏡の破片に顔を映すが、それは自分の断片を映すのみ。ついに映像を映していたスクリーンの紙を破いて大きな鏡を出現させる。映し出される真実の自分?(そこにはターリばかりでなく,彼女を見つめる多くの観客の姿も映る)。ターリはそこで後ろ向きになってかつらを取り,顔に髭を描いて「男装」し,床に置いた鉄板を激しく揺すり,踏み鳴らす。ダンダン!ダダダン!!ダッダダダン!!!「もう鉄の音は嫌だ!」と叫んで,このパフォーマンスは終わった*16 。
セクシュアリティと民族の問題をいっしょに語ることの無謀さを,一方でイトー・ターリは危惧するが,日本社会の中の疎外と差別において両者は共通するだろう。どちらも簡単な問題ではない。そして鉄板を踏み鳴らす音は,そのまま出光真子の映像の兵士たちの軍靴の音,銃声にオーヴァーラップする。ジェンダー,セクシュアリティや出生などの個人的な問題への社会の抑圧は,おおがかりな国家的な抑圧に容易に繋がっていく。
そもそもこの展覧会の発端になったテレサ・ハッキョン・チャの作品は,1963年,12歳で家族とともに韓国からアメリカに移住し,ディアスポラとして,国家や言語の境界で揺れ動くことを余儀なくされた,自己のアイデンティティの表現から始まったものである*17 。ハッキョン・チャの出品作品《Passages Paysages》(移行/風景)は,3つのモニターに同時平行に映し出されるヴィデオ・インスタレーションであり,そこには彼女の遺作『ディクテ』(1982)にも登場する母の写真や,山水画,彼女自身の手のクローズアップ(結ぶ手,開く手),三面の窓のある室内,風景がゆるやかに展開する図4。3つの画面は時に一致したかと思うと,またすぐにそれぞれ異なるものに「移行」する。映像のフーガ(遁走曲)。その不安定さは,ひとつの場所に同一化することのできない「移民」としての自己を表現しているともいえるが,しかし今,日本でも,誰が確固とした自分の位置を違和感なく規定し得るだろうか。

高橋芙美子のパフォーマンス《ボディー わたしの着ているもの》も,自分自身の女性身体に被せられた性的イメージに対する違和感を,マネキンのボディーを使って異化し,外在化しようとするものとも見えた。自分の黒い着衣の胸やお尻の部分を鋏で切り取り,マネキンに貼りつけていくが、それは彼女の(虚偽の,仮初の)肉体の表皮だろうか。
ハッキョン・チャの作品の突き付ける問いに対して,韓国と日本のアーティストたちはそれぞれ誠実に向き合ったと言えよう。さらにこの問題は,シンポジウム「Co-responses on the Borderline ―境界線上に立って,互いに応答する/日韓女性の アートと心」でも,異なる立場から応答がなされた。何よりイトー・ターリ,パク・ヨンスク,尹錫男(ユン・ソクナム)ら出品アーティストの自作を語る言葉は,力強くユーモアに満ちていた。そして,レベッカ・ジェニスン,池内靖子,李静和,笠原美智子ら,女性学や演劇論,政治学の研究者,美術館キュレーターたちの応答も,アーティストの作品に呼応して,現在の世界の動き(冒頭に書いた,イントレランスの時代)への危惧とそれを可視化する(書き続ける)意思に貫かれていた。なかでもレベッカ・ジェニスンによる,「ボーダー・トラブル/ボーダー・トーク:『別の場所で見えること,聞こえること』」と題した講演では,「ボーダーラインに立ち,体や心に不安や恐怖を感じているからこそ,さまざまなことがよりはっきり見えてくること」が指摘され,ボーダーラインを攪乱する「境界線上の女たち」が,そこで「見える/聞こえる」ことを語り続けるのがこの展覧会の重要な意義であること,それと同時に「境界」は権力装置であり,境界線上の自分の状況について沈黙を破って語ることができない場合があり,その一方でまた「境界」を語ることは,他人を排除したり,圧迫したりする危険性を孕むことも忘れてはならないという,最も重要な前提が語られた。ジェニスンの言うように,「だからこそ,対話Co-responsesが,一方的ではない話が,聞くことが必要」なのであり,それこそが,この展覧会とシンポジウムの目的であり,実践されたことであろう。
  
註
*13 予算不足から,韓国から新作の彫刻を運べないために,鎌倉画廊の個展の時に発表して日本にあった旧作を中心にインスタレーションしたというが,そのためにかえって1990年代の「母の眼」を中心に据えた作品を,2004年の女性たちの現在に応答させることができた。
*14 ユン・ソクナムの作品については,以下の拙論を参照。小勝禮子「美術の制作と受容をめぐって―社会,ジェンダー,その他の要素」,芸術批評誌『REAR』no.4,2003年10月,pp.21-29。小勝禮子「身体・自然・女性―歴史を担う女性身体―」,『diatxt.』no.11,2003年11月,pp.108-115。
*15 筆者も家族の秘密を書いてみた。しかし箱に入れずに持ち帰った。いまだ心は解放されていないのかも知れない。知人は書くこともせずに帰ったが,そのことが心に引っかかり,帰りの車中で何も書かなかったことを後悔したという。いずれにせよ,観客の心に家族の問題を問いかけ,かき乱す効果を持ったといえよう。
*16 8月16日,シアターXで再演された「虹色の人々」では,最後に叫びはなく、替わりに椅子の上に立ったターリが,夥しい数の鮮やかな虹色のスーパーボールを鉄板の上に滝のように落とした。その音と色彩の美しさは、初演の終わりと対照的であった。舞台からこぼれ落ちた玉は観客席に至り、観客はその小さい玉を舞台に放り返した。
*17 池内靖子「境界に立つということ テレサ・ハッキョン・チャの『ディクテ』を読む」,『現代思想』特集=フェミニズムの最前線,2004年6月,pp.204-219。
top
|